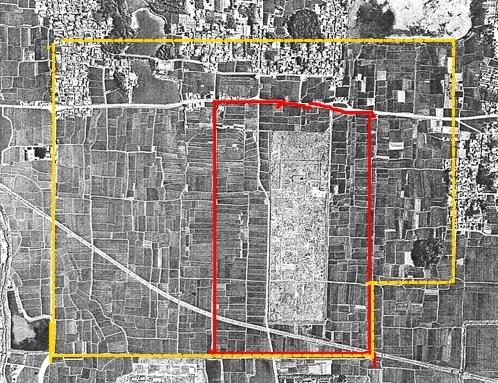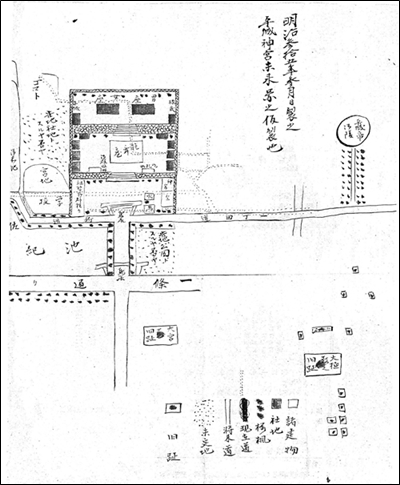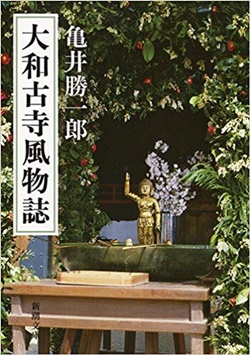新しき年の初めの初春の今日降る雪のいやしけ吉事 ⑳4516
(大意)新しい年が始まる初春のおめでたい今日、さらにめでたくも雪が降っている。たくさんの良きことがありますように。
天平宝字3年(759)正月一日、因幡の国庁であった賀宴で守(長官)の家持が詠んだ歌である。前年の6月、家持は因幡守に任じられ、因幡で迎える最初の正月だった。正月の大雪は、その年の豊作の瑞兆とされる。「新し」、「初」、「雪」、「吉」とめでたい言葉を重ねて世の平安と繁栄を願ったのである。この場と家持の立場にふさわしい歌であり、もって歌集の掉尾を飾るに考え抜かれた一首であった。
この時、家持は42歳、『万葉集』には16歳からこの歳までの作品、470首あまりを収録する。彼はそれから26年を生きたが、後半生の歌は残っていない。あれほどの歌人であり、宴会やそこで歌を詠むことも官僚としての彼には仕事の一つであるから、詠まなかったのではなく、残らなかったと考える方が合理的であろう。しかし、何かにつけ歌によって感情と思いを表現してきた彼の突然の「沈黙」は、我々には彼が歌と別れて人生という荒波の彼方へ去ったようにも感じる。だから「いやしけ吉事」とは、別れのまたは旅立ちの挨拶のようにひびく。それからの家持がたどった足跡を追ってみたい。
大伴家持は養老2年(718)、大伴旅人を父として生まれた。実母は不明であるが、天応元年(781)に家持が母の喪に服した記録があり、このとき家持は64歳であった。母は長寿だったことになる。旅人は晩年、太宰帥として筑紫大宰府に赴任し、家持も同行した。旅人は天平3年(731)に67歳で薨去し、このとき従二位大納言であった。彼は『万葉集』に七十首余りの歌を残したが、詠まれたのは60歳を過ぎしかも晩年の3年間に集中している。家持の享年は68で父とほぼ同年齢で亡くなったが、歌が詠まれた期間は正反対の好対照をなしている。
家持は内舎人(うどねり)として官僚コースをスタートした。内舎人は帯刀し、宮中の宿直、天皇身辺の警護・雑事にあたる。この時期に多くの女性と相聞歌を交わしている。天平17年(745)、28歳で従五位下に昇叙した。翌年に越中国守に任官。天平勝宝元年(749)に従五位上に昇叙。天平勝宝3年(751)に少納言に遷任されるまで5年間赴任し、この間の越中での歌が150首余りにのぼる。北国の風光の中で家持がもっとも輝いていた時期である。
京に戻った頃も、左大臣橘諸兄が太政官首班として長くその地位にあったが、その力には陰りが見え、光明皇太后をバックにした藤原仲麻呂が実権を振るうようになっていた。
天平勝宝5年(753)、この年に有名な春愁絶唱3首が詠まれた。
春の野に霞たなびきうら悲しこの夕影にうぐひす鳴くも ⑲4290
我がやどのいささ群竹吹く風の音のかそけきこの夕かも ⑲4291
うらうらに照れる春日にひばり上がり心悲しもひとりし思えば ⑲4292
天平勝宝6年(754)に兵部省少補(次官)に任じられる。翌年、防人交代の業務のため難波に出向、各国より進上された防人の歌を選別し記録した。天平勝宝8年(756)、聖武上皇崩御。この年、同族の出雲守大伴古慈斐が朝廷を誹謗した廉で失脚する事件があった。衝撃を受けた家持は「族を喩す歌」を作る。武の名門として代々天皇に仕えてきた栄誉を振り返り、その名声を汚さぬように同族に呼びかけた長歌である。
翌年、橘諸兄が薨去。仲麻呂の専横が目立つようになる。その状況で仲麻呂の排除を企んだ橘奈良麻呂の陰謀が露見する。これには大伴氏の有力者も加勢していた。大伴古麻呂・大伴古慈斐・大伴駿河麻呂・大伴池主・大伴兄人らが獄死や流刑に処せられた。池主は家持が越中守であったとき部下の越中掾(じょう)であり、歌のやりとりを頻繁に行った間柄である。もし家持が事件に関係していたら、『万葉集』は現在見る形と大分変わっていただろう。
天平宝字2年(758)に因幡守に任命されたのは必ずしも左遷とは言えないが、気になる大伴氏を中央から遠ざけようという意図が見えないこともない。天平宝字6年(762)、信部大輔(中務大輔)に任じられ帰京する。だが翌年、藤原宿奈麻呂が仲麻呂の暗殺を計画したとき家持も関わっていたらしい。捕縛された宿奈麻呂は罪を一人で被ったため、家持は放免されたが、翌年、薩摩守に左遷されたのは報復人事であったと思われる。この年に恵美押勝の乱があり、仲麻呂は没落する。
称徳天皇が重祚し道鏡が台頭する。しかし家持の官位は変わらず、神護景雲元年(767)に太宰少弐(次官)となる。家持の身辺が慌ただしくなるのは、称徳天皇が崩御し道鏡が追放され、光仁天皇が即位した宝亀元年(770)からである。民部少輔に任官、その3ヶ月後に左中弁中務大輔に遷任、さらに21年ぶりに昇叙があり正五位下となった。翌年に従四位下へ昇叙。宝亀3年(772)に式部員外大輔を兼務、これ以降の官職を見ていくと、相模守→左京大夫・上総守兼務→衛門督→伊勢守とめまぐるしく変わっていく。宝亀8年(777)には従四位上、翌年に正四位下に昇叙する。そして宝亀11年(780)に待望の参議に就いた。国政に関わり政策を審議できる役職である。右大弁も兼務する。このとき63歳であった。
天応元年(781)には桓武天皇が即位した。それとともに右京大夫、春宮大夫を兼任した。春宮大夫は皇太子・早良親王の宮を司る組織の長である。この年には従三位に昇叙し左大弁を兼務した。光仁上皇が崩御したときは、山作司(造陵長官)を指名されている。
延暦元年に氷上川継事件が起きる。宮中に兵仗を帯びて闖入した川継の資人(従者)が捕縛された。自白したところによれば、川継が味方を募って謀反を起こそうとしたという。氷上川継は天武天皇の皇子・新田部親王の孫でおり、父は塩焼王、母は聖武天皇の娘の不破内親王である。天武系の血筋をひく一族は、天智系の桓武天皇には警戒すべき存在であった。このため、この謀反が事実なのかフレームアップなのか歴史学者の説もわかれる。川継は流罪となり、一族縁者が罪を着せられた。これに家持も連座して職を解かれた。しかし、4ヶ月後にはもとの官職に復任している。嫌疑をかけられたものの晴れたということだろうか。
復任間もなく陸奥按察使(むつあぜちし)鎮守将軍に任じられた。対蝦夷政策を推進し、陸奥・出羽二国の行政と軍事を管轄する官職である。その拠点は多賀城にあった。家持は65歳であり、辺境での任務は大きな負担を意味しただろうが、武門の誇り高い彼には期するところがあったかもしれない。父・旅人も64歳で太宰帥に赴任したが、晩年での父子共通したこのような待遇に藤原氏から疎外された大伴氏の悲哀を感じる。東宮大夫は兼務している。延暦2年(783)には中納言に昇進している。翌年には持節征東将軍に任命された。天皇からじきじき節刀を授けられ蝦夷を征討する前線の任務を与えられたのである。この頃、京では長岡京遷都計画が進行していた。その中心にいたのが、従三位中納言藤原種継だった。桓武天皇に抜擢されて力を振るう種継は同じ中納言ながら家持より20歳年下で、辺境に追いやられた老人には中央政界で活躍する種継への複雑な思いが生じたかもしれない。
延暦4年(785)の4月、家持は奏上し、陸奥国に多賀郡と階上郡の二郡を新設することを具申し許可された。同年8月28日の『続日本紀』に家持の死去を伝える記事が載る。享年68。家持は従三位であるから「薨去」となるはずであるが、そうならないのは理由があった。9月24日、長岡京造営工事を監督していた種継に矢が射かけられ、翌日亡くなった。ただちに犯人が捕らえられ数十人に上った。大伴継人、大伴竹良、大伴真麻呂、大伴湊麻呂、佐伯高成ら、大伴氏一族と東宮関係者が多く関与していた。彼らが白状したところでは、家持が大伴氏と佐伯氏に呼びかけて種継の排除を狙ったという。多くの者が斬首され流罪となった。家持はすでに亡くなっていたから除名すなわち生前の官位と官職が剥奪された。そのため死亡記事は「死去」となった。家持の長男、従五位下右京亮の永主は隠岐に流されている。累は早良親王におよび廃太子となったが、無実を訴え淡路国に配流される途中、絶食して亡くなったという。
この事件の背景として、長岡遷都をめぐる対立、次期皇位をめぐる争いがあったと言われる。長岡遷都は桓武天皇の独断で朝廷内では反対意見が根強かったらしい。中納言の太政官にありながら蚊帳の外に置かれた家持も強引な遷都は快く思えなかっただろう。また桓武天皇には安殿(あて)皇子がいたため、早良親王の皇太子としての地位は危うくなっていた。その親王を東宮大夫として支えていたのが家持である。安殿皇子の母、藤原乙牟漏は種継同様、藤原宇合を先祖にする式家であり、ここでも家持と利害は対立した。
事件の黒幕に家持がいたというのは、十分理由のあることだが、疑問もいくつかある。家持の陸奥赴任は薨去するまで3年間におよんでおり、計画にどこまで関われただろうか。また種継一人を殺害することで事態がどのように変わると思ったのだろうか。結局、最悪の結果しかもたらさなかったのであるが、これまでいくつもの危地を賢明に慎重にくぐり抜けてきた彼がこれを予想できなかったとは思えない。これは一種の暴発であるが、生涯の最後に堪忍袋の緒が切れたのだろうか。その代償は大きかった。
大伴家持は名門貴族の御曹司に生まれ知性と才能に恵まれ、万葉集随一の歌人として名を残した。多くの女性と恋愛し、政治家としても従三位中納言の地位に上りつめ、当時としては68歳の長命をまっとうした。羨ましく輝かしい人生を送ったように思うのだが、その足跡をたどっていくと試練と緊張の連続に耐え続け、不本意でも与えられた任務をこなした生涯が見えてくる。運も彼に味方した。延暦25年(806)、桓武天皇は臨終のまぎわに詔した。「延暦四年の事に縁りて配流されし輩は已に放還(許し帰す)せり。今思うところあり。存亡(生死)を論ぜず。宜しく本位に叙すべし」(『日本後紀』)。怨霊に悩まされた天皇は、種継事件で罰せられた者すべてを許し、家持も従三位に復した。この名誉回復がなければ、『万葉集』は歴史の闇に葬られていたかもしれない。
参考
鐘江宏之『大伴家持 氏族の「伝統」を背負う貴公子の苦悩』山川出版社
藤井一二『大伴家持 波乱に満ちた万葉歌人の生涯』中公新書
小野寛編著『大伴家持大辞典』笠間書院
青木和夫他校注『新日本古典文学大系 続日本紀』岩波書店
伊藤博校注『万葉集』角川文庫
坂上康俊『日本の歴史5 律令国家の転換と「日本」』講談社