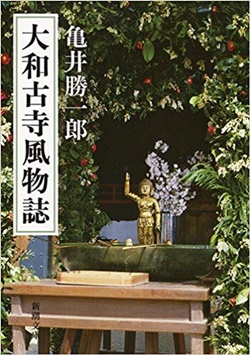
私がはじめて新潮文庫版『大和古寺風物誌』を読んだのはかれこれ半世紀ほど前である。著者は1966年に亡くなっていたが、有名であったし、この本が人気のあることはなんとなく知っていた。タイトルが牧歌的であるのにもひかれた。しかし甘美な詩情あふれる大和の歳時記風エッセイという予想に反して、内容は高校生の私の理解力を超えていた。だが、それにもかかわらずこの本への関心は消えず、私の中で『大和古寺風物誌』=大和路のイメージがいつのまにか生まれていた。何が私をひきつけたのか。いま考えると、本書の強い文学性であったのだと思う。美術史家の町田甲一は、『古寺巡礼』と『大和古寺風物誌』の仏像鑑賞が「主観的文学的哲学的」であり、仏像の客観的な理解ではないと批判したが、それは『大和古寺風物誌』についてより言えることであろう。でもそこが逆に私を惹きつけていた所以なのである。
古典の地で図られた再生
亀井勝一郎は1907年、北海道函館に生れた。東大美学科在学中「新人会」に加わり大学を中退。1928(昭和3)年、治安維持法違反の疑いで検挙される。保釈後日本プロレタリア作家同盟に所属するが転向して、1935年同人誌「日本浪曼派」を創刊。文芸評論家の道に進む。戦後は宗教的立場から文明批評を試みる。『日本人の精神史研究』で菊池寛賞受賞。1966年死去。『亀井勝一郎全集』全21巻補巻3がある。
亀井と大和との出会いは1937年(昭和12)、30歳の時であった。20代初期のマルクス主義革命運動への参画と挫折・転向を体験し、文芸評論の道にスタートを切ったばかりである。思想的な模索と人生への探求が彼の中で渦巻いていた時期であった。大和の古寺巡りを始めた動機を彼は次のように書く。
「はじめて古寺を巡ろうとしていた頃の自分には、かなり明らかな目的があった。すなわち日本的教養を身につけたいという願いがあった。長いあいだ芸術上の日本を蔑ろにしていたことへの懺悔に似た気持もあって、改めて美術史をよみ、希臘(ギリシャ)・羅馬(ローマ)からルネッサンスへかけての西洋美術とどう違うかということや、仏像の様式の変化とか、そういうことに心を労していたのである。仏像は何よりもまず美術品であった。そして必ず希臘彫刻と対比され、対比することによって己の教養の量的増加をもくろんでいたのである。私においては、日本への回帰――転身のプログラムの一つに「教養」の蓄積ということが加えられていた。己の再生は、未知の、そして今まで顧みることのなかった古典の地で行われねばならなかった。古美術に関する教養は自分を救ってくれるであろうと。」(新潮文庫『大和古寺風物誌』71頁)
昭和12年は日中戦争が始まった年であり、国内での「愛国心」の高まりがあり、国粋主義的な思想で社会が染められていく時代だった。亀井の「日本回帰」もその風潮に棹さす一面のあったことは否定できない。だが時代の影響のみに限定することはできない。亀井は北海道に生まれ高校は山形で過ごした。日本の古典文化から離れた北国、東国の風土で育ち、当時の知的青年らしく西欧の思潮を吸収して精神を形成した。思想において人生において紆余曲折した彼の前に新たな世界として日本の古典が現れた。そういう意味では内的な必然性に促されての「古典の地」大和への旅であり、ここでの「己の再生」が希求されたのである。
大和へ旅するまでは彼にとって仏像は親近感を覚えるものではなかった。西欧の教養で自己形成していた彼は、当然ながら西欧の古典美術に心ひかれていた。大和に向かった当時の知的青年たちのバイブルは『古寺巡礼』であったが、彼らは多かれ少なかれ西欧の学問を仕込んだ和辻と知的環境を共有し、亀井もまた変わりなかった。『大和古寺風物誌』に登場する寺院や仏像は、『古寺巡礼』と共通するところが多い。ギリシャ古典を起点とする美意識がともに深く内面化されているからである。
仏像は仏である
美術鑑賞の対象であったはずの仏像は、だが、亀井の前に異なる姿を現す。法隆寺の百済観音の前に彼は立った。
「仄暗い堂内に、その白味がかった体躯が焔のように真直ぐ立っているのをみた刹那、観察よりもまず合掌したい気持になる。大地から燃えあがった永遠の焔のようであった。人間像というよりも人間塔――いのちの火の生動している塔であった。胸にも胴体にも四肢にも写実的なふくらみというものはない。筋肉もむろんない。しかしそれらのすべてを通った彼岸の、イデアリスティクな体躯、人間の最も美しい夢と云っていいか。殊に胴体から胸・顔面にかけて剥脱した白色が、光背の尖端に残った朱のくすんだ色と融けあっている状態は無比であった。全体としてやはり焔とよぶのが一番ふさわしいようだ。」(同58頁)
それは、「仏像は、私にとってもはや美術品でなく、礼拝の対象となった」瞬間であった。このとき亀井に宗教的な回心が起きたのである。我々としては「何故」と問いたいところであるが、おそらく「宿命」としか言いようがないだろう。起きるべくして起きたのである。かくして「仏像は拝みに行くものだ」という信念が本書を貫くテーマとなり、この書の独自性となる。『古寺巡礼』などに導かれて仏像の美術的鑑賞が当然となった時代に、この宣言は顔をはたかれたような訴求力を持つ。「仏像は信仰の対象であった」ことを改めて気づかせてくれる。読者のなかには共感を覚える方もいるだろう。しかし現代人は昔の善男善女のように仏の前に素朴にひざまずけるだろうか。ここに、ひときわ鋭い感性と高い教養をそなえた現代人がいかに宗教に目覚めて思索を深めていくかという求道の物語が生まれる。
美を入り口にした信仰
著者がとくに心を揺さぶられた仏像は、法隆寺百済観音、中宮寺半跏思惟観音、法輪寺虚空蔵菩薩、薬師寺薬師三尊、東大寺三月堂不空羂索観音である。それぞれは「大地から燃えあがった永遠の焔(百済観音)」、「生存を歓喜しつつ大地をかけ廻った古代の娘(思惟観音)」、「光の循環のメロディがそのまま仏体の曲線でありまた仏心の動きをも示している(薬師三尊)」、「一切を黙ってひきつれてなおゆるぎなく合掌する威容は、天平のあらゆる苦悩と錯乱の地獄から立ちあらわれた姿(不空羂索観音)」などと形容される。情熱的で想像力を喚起する巧みなレトリックは、これらの仏像を強く印象づける。著者の仏に没入する様子には並々ならぬものがあり、信仰の告白のようにも思える。
だが一方で本書は、美を入り口にした「仏像鑑賞」の書という性格ももつ。和辻哲郎は感覚と信仰を対立的にとらえたが、亀井はふたつを両立させる。「美を無視して信心のみから仏を仰ぐことは出来かねるのだ。美しくなければ私はその信仰を疑う」(170頁)。だから本書の奔放で想像力に富んだ「美術的鑑賞」は、『古寺巡礼』と好一対をなして読者に受けいれられてきた。
歴史への関心
著者は、仏像の様式や大陸からの伝来、異文化との交雑に触れることはほとんどない。関心が寄せられるのは、造仏された歴史的背景である。飛鳥時代から白鳳期、奈良時代にかけて『日本書紀』や『続日本紀』に記録された古代史に注目する。支配層の同族相食む凄惨な戦いはやまず、疫病、災害、飢饉に民は苦しむ。このような状況に心を痛め仏の祈りに救いを求めたのが、聖徳太子、天武天皇、持統天皇、聖武天皇、光明皇后だとする。飛鳥、白鳳、天平の仏像には、この貴人たちの祈りと願いが結実しているという。とくに聖徳太子と上宮王家の自己犠牲に菩薩行の実践を見て、太子に帰依せんとする心情がつづられる。古代史の叙述にはかなりの分量があてられた。これは大和の仏像鑑賞として歴史の知識が重要であることを教える啓蒙的な役割を果たしたことだろう。
大和の風景への愛着
亀井は昭和12年の秋にはじめて奈良を訪れ、それから毎年のように春秋の旅行を繰り返し、この間につづった紀行を単行本にまとめ17年に出版した。さらに敗戦後すぐに書いた文章を加えて昭和28年に新潮文庫の『大和古寺風物誌』を刊行した。数年にわたって何度も奈良を訪問したことで奈良の風土になじみ、いろいろ考えることも多かった。
この頃の奈良の寺は多くがまだ廃仏毀釈の打撃から立ち直れず、千年の有為転変の痕を刻むかのような荒廃の雰囲気を漂わせていた。亀井はしかし荒廃と衰亡に心ひかれた。そこに歴史の生命を感じた。これに対し法隆寺が名声の故に「もったいぶって」復興する姿に嫌悪感を示し、その観光寺院化を懸念した。
亀井は奈良の風景にやすらぎ癒やされた。とくに斑鳩の里と西ノ京への賛美を惜しまない。
「中宮寺界隈かいわいの小さな村落を過ぎて北へ二丁ほど歩いて行くと、広々とした田野がひらけはじめる。法隆寺の北裏に連なる丘陵を背にして、遥に三笠山の麓にいたる、古の平城京をもふくめた大和平原の一端が展望される。大和国原という言葉のもつ豊かな感じは、この辺りまで来てはじめて実感されるように思う。往時の状景はうかがうべくもないが、田野に働く農夫の姿は、古の奈良の時代とさして変ってもいないだろう。春は処々に菜の花が咲き乱れて、それが霞んだ三笠連山の麓までつづいているのが望見される。畔道に咲く紫色の菫、淡紅色の蓮華草なども美しい。おそらく飛鳥や天平の人たちも、この道を逍遥したことであろう。陽炎のたち昇る春の日に、雲雀の囀りをききつつ、私のいつも思い出すのは、「春の野に菫摘まむと来し吾ぞ野をなつかしみ一夜宿にける」という万葉の歌である。この歌の気分がここで一番しっくりあうように思う。
しかし大和国原の豊かさを偲ぶという点では秋の方が更にふさわしい。今年はとくに豊作の故でもあったろうが、眼のとどくかぎり一面に実った稲の波である。透明な秋空の下に、寸分の隙もなく充実していて、黄金の脂肪のような濃厚な光りを放っていた。稲穂が畔道に深々と垂れさがって、それが私の足もとにふれる爽やかな音をききながら幾たびもこの辺りを徘徊した。豊作というものがこんなに見事なものとは知らなかったのである。心からの悦びが湧きあがってくる。」(同118頁)
「奈良近郊でも私のとくに好ましく感じたところは薬師寺附近の春であった。西の京から薬師寺と唐招提寺へ行く途中の春景色にはじめて接したとき、これがほんとうの由緒正しい春というものなのかと思った。このような松の大樹や、木々の若葉や麦畑はどこにでもみられるかもしれない。しかしその一木一草には、古の奈良の都の余香がしみわたっている。人間が長きにわたって思いをこめた風景には香があるのだろう。塔と伽藍からたち昇る千二百年の幽気が、この辺りのすべてに漂っているように思えた。‥‥
土塀といえば、私は大和をめぐってはじめてその美しさを知った。‥‥大和古寺の土塀や奈良近郊の民家の築地は、そう鮮かなものではなく、赤土のまじった、古びた地味な感じのするのが多い。よくみると繊細な技巧の跡がうかがわれる。そして崩れたままにしてあるところに、古都の余香が、或は古都のたしなみとも云うべきものが感ぜられる。」(同136頁)
昭和初期の斑鳩と西ノ京の風景である。もはや二度と見られない風景が言葉により鮮やかに描かれ残されたことに感謝したくなる。写真家の入江泰吉は『大和古寺風物誌』を携帯して大和を巡り歩いたそうだ。この風景描写は確かに入江の写真に通じている。入江の作品の原点はここにあるかもしれない。
主要参考文献
亀井勝一郎『大和古寺風物誌』新潮文庫
亀井勝一郎『我が精神の遍歴』日本図書センター
武田友寿『遍歴の求道者亀井勝一郎』講談社
町田甲一『大和古寺巡歴』講談社学術文庫
碧海寿広『仏像と日本人』中公新書