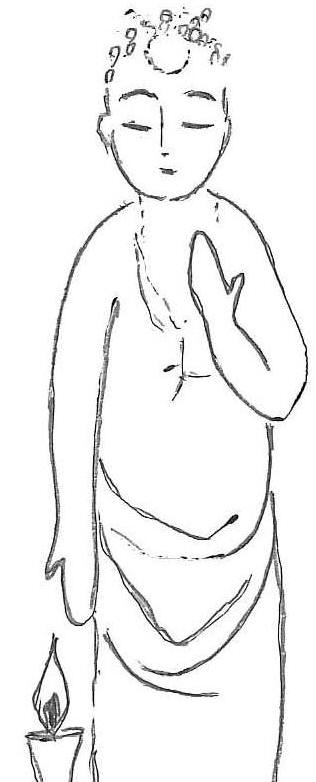奈良市北部の佐保丘陵の裾にある名刹、興福院(こんぷいん)は、一般にはあまり知られていないが、観光・史跡ガイドにはほぼ常連で掲載されている。予約すれば拝観できるというが、最近はなぜか断られることが多いという。実は私もまだ拝観していない。ガイドやネットの写真を参考に簡単に紹介しておこう。50m程の参道を歩くと四脚門の大門に迎えられる。石畳、石階、植え込み、生け垣が美しくて落ち着いた境内に茅葺きの客殿が目立っている。正面の高所に建つ本堂(重文)は、寄棟造、本瓦葺きで、屋根は中程に段差を設けて瓦を葺く錣葺(しころぶき)である。いずれも江戸時代初期の寛永年間の建立である。本尊は木芯乾漆阿弥陀如来像(重文)で奈良時代の作だ。
創建は寺伝では奈良時代にさかのぼるとされるが、近世までの歴史は不明である。現在は浄土宗の尼寺であり、大和大納言の郡山城城主豊臣秀長が200石を寄進したことをもって再興された。秀長の未亡人が2世住職になっている。その頃の寺地は奈良市の西の京、近鉄橿原線尼ヶ辻駅の近くにあった。徳川の天下となって3代将軍家光が寺領を安堵、現在の本堂、客殿、大門はこの時期に造営されている。1665年に現在地に移転した。
尼辻(あまがつじ)という地名の起原はふたつの説があって、鑑真和上が唐招提寺を創建するにあたって土を舐めたら甘かったので良い場所だと喜ばれたことから、「甘壌」が「尼辻」になったという説と、興福院があったからだという説である。両説の真偽はともかくとして、私はかねて尼辻に興福院があったということに関心を抱いていた。かつて存在したが、今は失われた廃墟、廃寺、史跡に私はとりわけ興味をかきたてられる。
だから、尼ケ辻に興福院の旧跡、墓地と井戸があると地元の方から教えられたときは、歓喜した。所在地を詳しく聞き出してすぐに出かけた。墓地は地元では「おふじさんのお墓」で通っているらしく、「おふじさん」とは秀長公夫人のことで、秀長公が一目惚れして城へ連れ帰ったという。
尼辻中町の路地は軽自動車がやっと通れるぐらいの道幅しかなく、しかも直角に曲がる箇所も多いから、車は途中までしか行けない。ただ旧跡見たさに杖を引いて細い路地を行ったり来たりした。築地塀が続いて入母屋造りの大きな木造民家が軒を接する集落である。墓地は家並みが途切れる一角にあった。周囲に雑木が茂り雑草で覆われ一見して荒れ地である。陰鬱な雰囲気に踏み込むのはためらったが、もちろん引き返すわけにはいかない。
古い墓石が間隔を開けて整列する。小さな舟形の墓石が多い。次に宝篋印塔が目立って、五輪塔は少ない。無縫塔もある。割れたり欠けたり傾いだものもあって、全体として朽ちた印象が強い。どの墓石の前にも茶色の陶器の花立てがひとつ突き立てられて、枯れ切った花がところどころに残る。敷地の広さの割には墓石は少ない。墓石のまわりは除草されているが、外れると夏草が茂り放題である。荒寥感と不気味さがつきまとう。
墓石に刻まれた文字を見てゆく。読めるものは少ないが、その中に「施主 東大寺大勧進上人 龍松院 公慶 元禄五年壬申八月十日」というのがあった。公慶(1648~1705)は元禄の大仏殿再建に功績のあった高僧である。敷地のほぼ中央にあって比較的大きな自然石の墓石だった。誰のお墓か分からなかったが、元禄5年は1692年であるから、すでに興福院が移転した後だ。歴史上に名高い人物の名前を認めて興奮した。おそらく戦国時代から江戸時代初期の興福院関係者の墓地なのだろう。居るほどに不気味さが募っていく。蚊にも刺されるので、写真を撮るとすぐに墓地を出た。
井戸は墓地から南東へ200mほど離れた一段低い町角にあった。直径1mほどの丸い井戸をフェンスが囲っている。その上から覗くと、中は雑草にさえぎられてよく分からない。腕を伸ばして撮った写真には、雑草越しに暗い影が見えて穴なのだろう。まだ埋まらずに井戸の形を保っているようだ。すぐそばに新しい祠があり、その前は広場になりきれいに整備されている。祠には座像の石仏が安置され「都大師 大正十四年」と印されてあった。
この後に地元の郷土史家の著書(松川利吉著『平城旧跡の村』)を読む機会があった。そこには、墓地は興福院の本堂があった場所であり、その南にあるドロマ池は「堂前の池」が訛ったとある。井戸もかつて村人が利用していたという。
『角川日本地名大辞典奈良県』は、江戸時代から使われていた興福院村が明治21年から尼辻村になると記す。しかし、興福院は小字名として残り、今も地元の人にはそう呼ばれているようだ。
墓地も井戸も標識や説明のボードはない。最近、史跡の表示や説明ボードの設置に力を入れる市町村が増えているような気がするが、やはり限りがあるだろう。すべての土地は来歴を持つ。それぞれは当事者の記憶に留まるが、同時に当事者とともに消え去っていくだろう。だが、中には多くの人々の記憶に残り語り継がれるものがある。興福院旧跡もそのようなものであった。多くの人といっても限られた人であり、明確な記録はないので記憶は変容し伝説に近づいていく。このような伝説に不意に出会うことは、この上のない喜びである。(2017/8/15記)
興福院旧跡墓地
興福院旧跡井戸